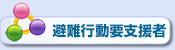いざというときのための避難に関する知識
災害が発生し、家屋内にとどまることが危険な状態になった場合は、落ち着いてすばやく避難する必要があります。その際には、子どもや高齢者などの要配慮者の保護を念頭に置き、近所の一人暮らし高齢者世帯などにも声をかけるなど近隣で協力することが大切です。また、避難所での生活をよぎなくされる場合も自主防災組織を中心にみんなで助け合いましょう。
避難の考え方(地震・風水害共通)
国内で感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が発生している、または発生しやすい時期の災害時の避難の考え方として、避難所へ避難することのみが避難ではなく、安全が確保できる場所へ避難する「分散避難」を取り入れます。親せきや知人宅への避難、ホテルや旅館などの宿泊施設への避難、近隣市区町村や都道府県をこえた広域避難、自宅が安全(強固、高所など)であれば留まる在宅避難、安全な広場などに停めた車での車中泊避難などを想定しましょう。避難のタイミングを見逃すな
- 市から避難指示などの避難情報が出たとき。
- 近隣で火災が発生し、延焼の恐れがあるとき。
- 津波、土石流、がけ崩れ、地すべりなどの恐れがあるとき。
- 自宅で火災が発生し、火が天井まで燃え移ったとき。
- 建物が倒壊する危険があるとき。
- 危険物が爆発する恐れがあるとき。
避難するときはこんな服装で

- ヘルメット(防災ずきん)をかぶる。
- 非常持出品はリュックサックに入れて背負う(両手が使えるように)。
- 長袖・長ズボンを着用。燃えにくい木綿製品がよい。
- 軍手や革手袋をはめる。
- 靴は底の厚い、はき慣れた物を。
避難時のポイント
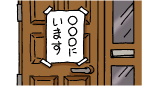
- 避難する前にもう一度火元を確認。ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーも落とす。
- 荷物は最小限の非常持出品に限る。
- 外出中の家族には避難先を記した連絡メモを目立つ場所に残す。
- 移動するときは、狭い道、塀や自動販売機のそば、川べり、ガラスや看板の多い場所は避ける。
- 決められた最寄りの避難場所へ徒歩で移動する。
- 子ども、障がい者、高齢者など要配慮者を中心にして避難者がはぐれないように。
防災ヒント
■避難所で過ごす


避難所となった体育館で過ごす被災者
自宅を離れて避難所で生活するのは大変不自由なことです。ストレスや過労から体調を崩してしまうこともあります。実際、東日本大震災や熊本地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)などの大規模な自然災害が発生した際に、長引く避難所暮らしが体力の弱い高齢者等の命を奪ってしまう悲劇が相次ぎました。避難している住民同士で助け合うことはもちろん、支援してくれる医師・看護師といった専門家や相談相手としてのボランティアなどを積極的に活用して、心身の健康を保つように努めましょう。