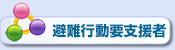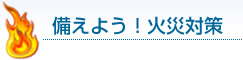火災を防ぐためには?
火災を防ぐためには?
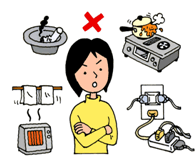
自分や家族の命を落としたり、大切な財産を失うことがないように、火災を防ぐためのポイントをきちんと学び、日ごろからみんなで注意し合うようにしましょう。
火災を防ぐためのポイント
放火対策を
ゴミは指定された当日の朝に出すなど、家のまわりに燃えやすい物を置かないように。車庫、物置などの戸締まりも忘れずに。
コンロから離れない
火がついている物から離れるときは必ず消すこと。コンロのまわりに燃えやすい物は置かない。着衣への着火にも十分注意を。
寝たばこ、ポイ捨ては厳禁
灰皿には水を入れておき、吸殻を捨てるときは必ず水にさらすように。火のついたたばこは放置せず、必ず消火の確認を。
風が強い日にたき火はしない
風の強い日や空気が乾燥しているところでのたき火は危険。必ず水を用意して、たき火の後は完全に消火したことを確認しよう。
マッチやライターで遊ばせない
子どもには火の正しい使い方、恐ろしさを教え、子どもの手の届くところにライターやマッチは置かないように。また、日差しの強いところでの放置に注意。
ストーブまわりを整理
衣類やふとん、カーテンなど、ストーブのまわりに燃える物を近づけないように。近くで洗濯物を干すのも厳禁。給油は完全に火を消してから行う。
配線まわりはきれいに
コードの上に物を載せたり、コードをまとめたり、たこ足配線をしないこと。コンセントまわりは定期的に掃除を。
住宅用防災機器を活用しよう
火災の発生を早く知る
■住宅用火災警報器

煙や熱を感知すると、警報音で知らせてくれます。平成16年の消防法改正により、設置が義務づけられました。
火災防止に
■安全装置付調理器具

異常な過熱や火が消えた際に、自動的にガスの供給を止めます。
■感電ブレーカー
地震の揺れを感知し、自動的に電気の供給を遮断するブレーカーです。
火災の被害を最小限に
■防炎品

火がついても燃え広がりにくい防炎品。カーテンやカーペット、寝具、エプロンなど。
■住宅用消火器
小型で軽量タイプの消火器です。
■簡易自動消火装置
火災の熱を感知すると、自動的に薬剤を放出します。
■住宅用スプリンクラー設備
火災の熱を感知すると、部屋全体に放水します。
消火器の使い方を覚えておきましょう
消火器の種類
消火器には、どんな種類の火事に適しているかを示すラベルが表示されています。使用目的に合った消火器を選びましょう。一般の家庭の場合は、万能タイプの粉末消火器か強化液消火器が便利です。
火災の種類 |
普通火災 | 油火災 | 電気火災 | |
|---|---|---|---|---|
木材・紙など一般可燃物による火災 |
灯油・ガソリンなどが燃える火災 |
電気設備など感電の恐れがある火災 |
||
 |
 |
 |
||
ラベルの色 |
白 |
黄色 |
青 |
|
| 消火器の種類 | 粉末消火器 |
○ |
○ |
○ |
強化液消火器 |
○ |
○ |
○ |
|
泡消火器 |
○ |
○ |
× |
消火器の使い方
(1)安全ピンに指をかけ、上に引き抜く |
(2)ホースをはずして火元に向ける |
(3)レバーを強くにぎって噴射する |
|---|---|---|
 |
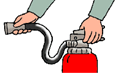 |
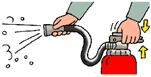 |
構え方

- 火の風上に回り、風上から構える。
- やや腰をおとして低く構える。
- 熱や煙を避け、炎には真正面から向き合わない。
- 炎を狙うのではなく、火の根元を掃くように左右にふる。
点検のポイント
(1)安全ピン |
|
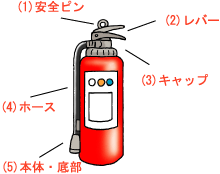 |
|---|---|---|
(2)レバー |
|
|
(3)キャップ |
|
|
(4)ホース |
|
|
(5)本体・底部 |
|
|
ゲージがある場合 |
|
「119」のかけ方を覚えておこう
通報時に伝える内容は、下記を参考に。
- 火災であることを伝える
- 災害現場の場所(住所)
- 何が燃えているか
- けが人や逃げ遅れている人がいるか
- かけている電話番号(携帯電話の場合は携帯電話の番号)
- 通報者の名前
携帯電話から通報する場合
災害地点を確認するのに時間がかかる傾向があります。携帯電話から通報するときは、次の点に注意してください。
- 所在や目標を確かめてから通報を。
- 携帯電話やPHSであることを伝える。
- 自動車からの通報は、安全な場所に停車してから。
- 通話終了後もしばらくは電話を切らないように。
- 途中で切れないように注意を。
- 高速道路では災害地点を正確に伝える。