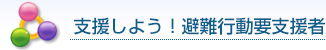要支援者との普段からの交流
普段から顔見知りの関係ができていると、災害時の支援がスムーズに進みます。時折声をかけるなど、日ごろの見守りを通じて顔の見える関係づくりをしておくことが支援の第一歩となります。いざというときだけの避難支援活動は役に立ちません。普段から要支援者と関わっている人たちが良好な関係を築くことで、地域の防災力を高めていくことにつながります。
日ごろからの関係をつくっておく
- 支援をする側とされる側が、あらかじめ顔見知りの関係になっていないと、いざというときに支援をすることは困難です。まずは要支援者の自宅を訪問して、お 互いに顔を合わせることから始めてみましょう。
- あいさつや声をかけるなどを通して、要支援者と日ごろから良好な関係をつくっておきましょう。
- 自治会などで開催する地域の行事など、気軽に参加できる機会を利用し、要支援者に声をかけてみましょう。
- 日ごろから顔見知りになっておくために、お茶会やサロンなど要支援者が気軽に参加できる会を工夫してみましょう。
- 外出が難しい要支援者やその家族の場合は、自宅を訪問する機会の確認などを通じて交流を深めましょう。

見守り活動を行う
- 日ごろの関係づくりが整ってくると、日々、地域が要支援者に気をかける(見守る)ことにより、孤立死などの防止にもつながります。
- 要支援者宅の「部屋の点・消灯」「カーテンの開閉」「洗濯物干し・取り入れ」「郵便ポスト」のような生活サインによる見守り活動もあります。
- 消防職員や消防団などによる要支援者宅への定期的な防火・防災訪問もひとつの方法です。防火指導や家具の転倒防止対策、非常持出品の紹介などのほか、避難時の支援体制の確認もできます。また、要支援者の状態の確認にもなります。
- 定期的に要支援者宅を訪問するケアマネジャーなどの福祉専門職や民生委員などは、要支援者の心身の状況や生活実態などに変化がないか確認することができます。心身の状況などに変化が見られたら、避難支援者と適時適切に情報を共有することも大切です。